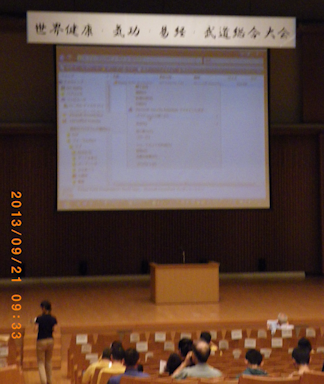武道
武道
先日(9/22、つまり世界気功フォーラムの翌日)、地元で市民大会があった。
日野市は土方歳三、井上源三郎など新撰組の幹部を輩出し、子孫縁者もいて武道が盛んである。特に前任の市長は新撰組によるまちおこしに熱心だった、新しい市長も試合の開会式に出席してスピーチするとともに観覧していた。


朝9:00の審判会議に始まり、小中学生、一般の試合、表彰式に続いて合同稽古と剣道づくしの一日だった。
中学生や(都立)高校生は、指導の先生が替わると見違えるように強くなったり、剣風が変わってくる。全体にのびのびとして思い切りの良い打ち込みで審判をしていても気持ちよかった。
それにしても、暑い一日だった。冷暖房完備のホールが昨年3月に完成して使用できる見込みだったが、東京国体で会場が従来の天然平屋根の体育館に変わった。動き回る子どもの試合は、汗だくで審判をした。
2013年10月12日
武道
先日、国立オリンピック記念青少年総合センターで開催された世界気功フォーラムに行ってきた。
3年ごとに開かれる世界大会で、主催者は少林寺第34代最高師範秦西平老師で、本場中国総本山少林寺武術気功の演武と魅力のワークショップ という。
パンフレット一面の主な出演者には、中国嵩山少林寺の現管長である釈永信、ホリスティック医学の第一人者であり終末期の癌治療に取り組む帯津三敬病院名誉院長など、そうそうたる顔ぶれである。
早く行かないと良い席が取れないと30分前につくようにばたばたして急いでいった。
間にあったと思って会場の建物へ入ると、 がらがらである。まだ、受付の準備中だった。
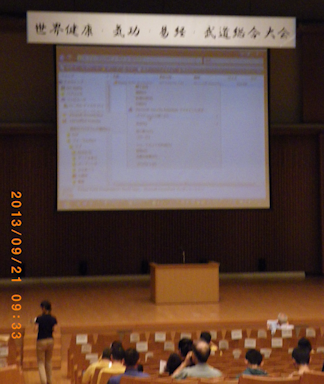
そこで思わぬ知り合い(中小企業診断士の研究会仲間)に会う。6月に中国嵩山少林寺へ行き、管長から直々に指導員の免状をもらったという、それで今日は手伝いのこと。
入っても良いというので、中に入ると、広い会場には、報道関係者が3,4人居てカメラチェックをしているばかり。良い場所をとって座ったが、いっこうに人が増えない。
プログラムをよく見ると、まだ1時間近くある! スケジュール帳は30分前になっている。早めにと考えて、予定を入れて、それを忘れてさらに30分前に着くようにしたので、1時間前に着いたのだ! 用意周到に見えて、間抜けなことをしてしまった(+_+)
いよいよ、オープニング。京劇風に銅鑼が鳴り、派手な爆転、横転をして入ってきた。そして、少林寺の演武。非常に楽しませる仕掛けだ。続いて、覆面レスラーのタイガースマスクも出てきた。二人で、木の床で投げたり蹴ったり、プロらしい動きだが、何か変。
#スが一つ多い。後で調べたら、大阪に実在の人物でタイガーマスクのパロディのようだ。なかなかキッチュなしかけ。
最初の主催者の講演が、中国訛の日本語で始まると、すぐに続けて中国語の逐次通訳、引き続いて英語の逐次通訳と3カ国語で行われる。なかなかインターナショナル!。出演も世界大会にふさわしく、日本、中国だけでなく、アメリカ、ルーマニアなどからの講演、実演と多彩であった。
気についておもしろい知見も得られた。高度な古代文化を誇った中国へ、仏教がインドから伝わってきて、道教、儒教へ影響を与えて、文化的な衝突と融合が行われた。儒仏道が東洋思想として融合をするつなぎとなるのが、気だという。
日本精神科医が精神的に病んでいるものは、マインドフル認知療法を進めようとしても、身体感覚が薄い。それには、気を感じることが治療に大きな効果を出すという。そのために、大東流合気(合気道の元となった)を活用しているという。実際に合気術を演じて見せた。西洋医学の素養がある人による発表は論理的で説得力があった。
東洋思想、気功、易経、少林寺、空手など多様な分野に触れて充実した一日だった。翌日は、ワークショップで更に詳しく聞けるプログラムだったが、私は、地元で剣道の市民大会があり、聞けなかった。
#中国嵩山少林寺の釈永信管長はメッセージのみで、帯津先生は影も形もなかった。やられたという気もするが、集客方法としてはたいしたものだ。それでも、興味深い内容も多く、十分もとは取れたと思う。
2013年10月8日
武道
防具入れキャリーバッグの車輪が落っこった
今日は私淑している剣道の先生の指導稽古があるというので、家から防具を担いで、…。近頃は、無精して、担ぐのではなく、キャリーバッグを引っ張って行こうと、玄関を出たら、ぽろっと車輪が落ちた。
見るとボルトが外れて、1本ころがっている。覗いてみると、残り3本は跡形もない。前から、1本取れていたのは知っていたが。全部ないとは、びっくり。
このキャリーバッグは、車輪が自慢のものなのに、…。元々の車輪が壊れたのを機に、ばかでかい車輪を東急ハンズで買って自分で底をベニヤ板で補強して取り付けたものだ。
防具専用ではないが、竹刀もちゃんと入れる(突っ込む)ところがあって、実に便利と周りに自慢をしていた。

大きいだけに重い車輪だったが、ベアリングがスムーズに回転して、道路を転がしても音がしない。ちょっと触っただけですいすいと動いてくれる。下り坂なら追っかけないといけないほどだ。

段差も平気でどんどんと乗り越えてくれる。その乱暴な扱いがいけないんだろうが。
ボルト1本はずれたところで、動かないという症状はなくても、兆候があった。東洋医学をやっている者としては、望診で未病を発見できていたのに、手当をしなかった。病気以前(未病)を大事にケアするのが売りなのに深く反省(+_+)
おそらく、先々週の稽古会の後に呑んだ勢いで引っ張り回して帰ったのが原因だろう。
しょうがないので、家に引き返して、とりあえず、四本着いている車輪からボルトを1本引っこ抜いて、2本で応急処置をして新宿のまんかい鍼灸院まで運んだ。新宿について、早速、東急ハンズへ行ってボルトナットを買って修理をした。
幸い、今日は患者さんは、午後からの予約だったので良かった。
治療も終わり、これから稽古に出かけます。ただ、今日も稽古が終わってから懇親会がばっちりとある。場所が新橋だから、おじさんの飲み屋には事欠かない。飲みながら先生から教わること、仲間との馬鹿話も剣道の醍醐味、勿論出席だ。帰りは、丁寧に車を引いて帰ろうと思う(酔いに任せず)。
※このバッグは、無理矢理手作り補強をしたものだが、手作りのものは自分で修理ができるから良いですね。キャリーバッグを使う人が多い昨今ですが、音ががらがらとやかましいのがほとんどです。大きな車輪を付けると静かになりますよ。私は、穴を空けるためにドリルも買いました。使い道も少なくて無駄なようですが、…。底に穴を空ける勇気がある人は試してください。
2013年9月13日
武道
この土日(7/27,28)、武道館で小学生の全国剣道大会があって、二日間審判をしてきた。
正確には、全日本少年少女武道錬成大会(剣道)という。全国から、大勢の少年剣士が集まり、広い武道館を16面に分けて、活気溢れる試合が展開された。剣道をする喜び、良い氣が充ち満ちていた。

武道館はミュージシャンのあこがれの舞台になって久しいが、元々は1964年の東京オリンピックの時に柔道競技を行ったのを嚆矢として、武道の殿堂である。剣道を行うものにとってもあこがれの舞台であり、参加の子どもも父兄も興奮、熱気に包まれている。
錬成大会という性格で試合だけで無く、基本稽古の判定勝負もある。切返し(左右面を打ちながら前進後退する)と打ち込みを5人の選手が元立ちの指導者にかかる。二組が同時に行い、それを見て優劣を判定するのだが、切返しでほぼ互角に上手だと非常に難しい。打ち込みで、片方が面や胴を外したり、応じ技をうまく返せないと、あきらかに差がつく。
しかし、それも互角だと、打突の強さや冴えとか体の中心軸がぶれていないか大人でも難しいところで見極めをすることになる。微妙な差が5人とも続いて、結果的に5対0になると大差がついたように見える。負けた子供達を見ると、がんばれよ、そんなに差は無かったんだ、良かったよと声をかけたくなる(会場では思うだけだが)。
試合は、あきらかに実力差がある対戦もあり、竹刀の一振り、二振り(数秒)で勝負がつくこともある。これも、わざわざ遠くから東京へ武道館へ来てかわいそうだが。しかし、これはこれで発憤材料となったり、思い出として将来の糧になっていくものと思う。
審判は非常に気を使い、体力も使う(動き回る選手の動きを追っかけて、というより先を読んで、常に最適の場所から選手二人を見、さらに他の審判二人の動き・旗を見ながらの動作)。特に子供達は、攻めのセオリーとか無くて飛び込んだり、動き回るので一瞬も気が抜けない。それでも、真剣な勝負を見ていると、すがすがしい気持ちになる。
剣道をやる子供達を見ていて、いつも良いなあと思うのは、男女とも表情が引き締まってりりしいことだ。瞬間的に勝負がつくので、稽古の中で集中力が自然と養われる所為だと思うが、近頃失われがちな事であり、剣道の徳目だ。
2013年7月30日
新しい記事 »